主に政治と経済について、思いついたことを語ります。リンクフリー、コピーもフリー
2008年11月17日12時54分 / 提供:ツカサネット新聞
ツカサネット新聞
追加経済対策で麻生首相が目玉として掲げた「定額給付金」。定額給付金は、財政投融資特別会計の剰余金を財源とし、総額1兆9,600億円。給付額を1人当たり12,000円、18歳以下と65歳以上には8,000円を加算するとし、所得制限は給付窓口となる各自治体が実情に応じて有無を含めて判断し、制限する場合は、所得1,800万円(給与収入概算2,074万円)を下限とすることを決めた。
これを受けて各自治体からは「丸投げだ」との批判が出ているが、首相は「迅速性と利便性、簡単なことが大事だ。」と述べ、やむを得ないとの認識を示した。
支給方法は、市区町村が世帯主に給付金の引換券を郵送し、世帯主が申請し、世帯主の金融機関の口座に市区町村が給付金を振り込む方式を軸に検討が進む見通しだ。実際に私達の手元に届くのは、来年の3月頃という見方が強い。
収入の現状を反映させるため、09年の所得の見込み額を基準とする案が有力で、年齢は09年1月1日現在とし、制限を超える所得があった人が給付金を受け取った場合は、市区町村の判断で返還請求を行うことが可能とする。
PR
中東ドバイに6,000社以上の外資が殺到ネット上の記事であるが、ドバイの「発展」ぶりが、よく分かる。2010年までに、UAEは石油依存を脱却し、依存率ゼロ%を目指すらしい。それまでに観光施設の整備などに努め、社会インフラ整備に励むようである。原油による富裕から外貨を稼ぐことで経済規模を拡張する戦略である。
10月の企業物価指数、前月比1.6%下落 素材価格急落で
日銀が13日発表した10月の国内企業物価指数(2005年=100、速報値)は109.8と前月より1.6%下落し、比較可能な1960年以降で最大の下げ幅となった。前年同月比での伸び率も9月の6.8%上昇から4.8%上昇へと鈍化。世界的な景気減速や投機資金の引き揚げを背景に原油などの素材価格が下がり、企業間取引の「物価高」が和らぎつつある。
企業物価指数は製品の出荷や卸売り段階で企業同士がやりとりする製品の価格水準を示す。品目別では石油・石炭製品の上昇率(前年同月比)が9月の37.8%から16.1%に鈍化し、非鉄金属、スクラップ類はそれぞれ16.7%、23.1%の下落となった。
また円高が進んだこともあって輸入物価指数は円ベースで前月比11.1%の下落となり、こちらも60年以来で最大の下げ率。9月に前年同月比61.5%上昇していた石油・石炭・天然ガスが27.7%に落ち着いたほか、とうもろこしや小麦などの価格下落で食料品・飼料が8.6%の上昇から7.3%の下落に転じた。(11:08)
世界のマネー、伸び鈍化 金融機関、投融資絞る
グローバルなマネーの伸びが急速に鈍化している。全世界で流通する米ドルの増加率は、今年10―12月期には10%すれすれに低下する見込み。金融機関の信用創造力が落ち、投資ファンドや産油国に集まっていた余剰マネーも急速に収縮しているためだ。こうした動きは実体経済に比べて肥大化した金融の自律調整の過程ともいえる。
国際通貨基金(IMF)などによると信用創造の元になる世界のドルの合計額は、 2008年1―3月期は前年同期比24.5%増加したが、10―12月期の伸びは同10.8%まで鈍化するとみられる。金融機関が融資や投資を絞っているのが背景。投資家からの解約が増えているヘッジファンドなども資産を圧縮している。(ニューヨーク=滝田洋一)(07:00)
国内の企業物価指数はとうもろこしや小麦など生活関連物資も含めて下落中。つまり、生活関連物資も一時の上昇傾向から下落へ進行中である。
日経新聞の滝田洋一の指摘も興味深い。マネーサプライとマネーの巡航速度も減少していることが覗える。世界の「マネー」量も絞り込まれ「デフレ」現象の到来を予感させる。う~ん、世界デフレか・・・・。個人や企業の経営者が頑張っても、デフレやインフレは中央銀行の対処によるのだから、個人や企業が対策は立ても、根本的解決にはならなく、どうしようもならんわな。インフレやデフレは、短期的、循環現象で、中央銀行の政策的管轄。
長期的には、原油などの資源価格も上がるだろうし、オイルそのものが枯渇するというオイルピークの問題もある。また、穀物生産も人口増加を背景に上昇し、未発達国での人口に対する食料不足による飢餓の兼念は、長期の問題、構造問題として政府の対応問題として現存し続けるのだろう。
長期の構造と短期の循環的問題を混同すると、おかしな議論が出てくる。昨今の原油高で、ピークオイルが原因だとする愚かな議論を「左」派系サイトなどで見かけたが、認識図式がそもそもおかしいのである。
原油や資源価格は、先物相場が主導したが、「需要と供給」を背景に基本的枠組みとして成立している。それはピークオイルによる原油枯渇で供給減少による需要が相対的に増えたという長期的、構造的問題とは全く別次元で成立する経済事象である。
前防衛大臣の石破 茂が田母神前空幕長の論文について論じている。靖国問題を語る論調は、かなり飛んでいると思うし、同調は出来ないが、それ以外は、ほぼ同調にたるものである。
筆者は大日本帝国は、大まかな時代性の区分としてある時期に「侵略国家」として転化したと考える。はじめから侵略性を持っていたわけではなく、また国際環境も列強を中心として殖民国家であった国家が、戦闘行為に依存する国家から非戦的な国家へ転化した時期があると考える。第一次世界大戦後、ベルサイユ条約、4カ国条約---日英同盟廃止(これは後に失敗であった気づく)、九カ国条約など、日本の海軍には屈辱的ではあったが、均衡軍縮への国際道程が存在した。この方向に軍事官僚は、加藤寛治など海軍は反発。この国際情勢の変化の認識を欠如させたことも大いに手伝って、「侵略国家」化したのである。そのように考えないと、東條英機の東京裁判での弁明である軍部官僚たちの「自衛戦争」であったという言説が生まれてくる根拠もうまく説明が付かない。
筆者は、日本が「侵略国家」になったと認識できる時期のメルクマールは、国家を機関として見るか、機関のみならず国民としても眺める視点、戦争は相手が必要であるから、当然にその当時の国際関係の内実を見る視点、第一次世界大戦が産業から兵器の戦車、戦闘機、などの高度化、大量化、技術を持つ兵士訓練、兵站補給など総力を導入しなければ戦争の目的の達成が不可能になったという視点などから眺めるべきであると思う。また、統帥権の干犯問題が、浜口雄幸内閣を攻撃する犬養毅、鳩山一郎の政友会によって切って落とされた。統帥権は、軍人を管轄するのは天皇の大権であるとする。軍縮を浜口雄幸内閣は唱えたが、それが統帥権を干犯するとの説を、犬養毅、鳩山一郎、政友会は反論したのである。こうした議論を経て、軍部は統帥権干犯、天皇大権を犯すべからず論を立て、軍人の分限を弁えず、独走していくことになる。
一方、逆の作用も統帥権は持っていた。統帥権は明治期の「軍人勅諭」に由来するが、ここでは軍人は、「世論に惑はす政治に拘らす只(ただ)々一途(いちず)に己か本分の忠節を守り…」という訓戒がある。軍人は、政治に容喙してはならないということであり、明治中期まで文民統制の機能も持っていたのである。「田母神論稿」は、武官としての「本分」からも大きく外れていることになる。
国家の機関の現場の人士とそれを統制する「政治」側が、それぞれの役割を守っていることが必要。軍人の文民の統制は、有権者が選択した「政治」の側の権限であり、文民統制をするのは飽くまで「政治家」側の管轄になる。政治家側が、軍事権力を支配するという「思想」が有権者側と当時の新聞というマスコミ、ラジオ放送に強固にあれば、軍部の「暴走」は防ぐことは満州事変以前であれば出来たと思える。
更に、その戦闘は短期決戦ではなく、何年間にも及ぶ長期の「消耗戦」へと変化した。それまでの「戦争」の局所的、職業的な軍人による「短期」の戦い方からマスコミから一般の国民の戦争協力支援までを総動員した「総力戦」への戦い方に変更された、その視点などから見るべきであると思う。
そのように考えると「通常」の国家から「侵略国家」へ転化したのは、満州事変以降であろうと思う。満州事変は、周知のとおり石原莞爾によって「軍人勅諭」に反する形で遂行されたが、石原莞爾---一般の国民には、石原莞爾の名は知られていなかった----は第一次世界大戦以前にドイツに留学、総力戦が如何になされるかを知ったとされる。そして、総力戦を長期の戦争を戦費を欠けず、また、資源を満州に求め、産業を興し、戦争をすることによって資源開拓を行うことによって資源無き日本でも可能だとした。
満州事変の後、国連の査察結果に大きく反発する形で、この時点からマスコミは、満州以前の非戦的な風潮から好戦的な論調が澎湃、転生、またそれに賛意同調する「政治家」「庶民」も増えたと思える。その意味で、侵略国家はこの時期に誕生したのである。戦前を大づかみに見すぎて、侵略国家であった、また、無かったという議論は、極端すぎて実りある論争にはならないのではないか。それが繰り返されるとすれば非常に残念な事態である。
参照
東京裁判 (講談社現代新書 1924)
米国からの民主勢力に強かったかつての自動車輸出バッシングなど起きることはないだろう。トヨタ、ホンダはすでに現地生産、現地販売に多くをシフトし、現地の雇用を生み出しているからである。
オバマの米国経済の建て直しと長期的戦略による米国の経済構造を変更させることが出来るのかが、日本の経済にとっては重大な事態でであるはず、である。一挙に「消費から貯蓄」への社会構造になるとすると、これはこれで、米国輸出依存の日本経済にとっては直近の大きな痛手である。 米国の消費で、輸出が支えられているアジア諸国家の成長性補償されている現状に目を向けるとその点が大きな短期的、経済循環的には関心事なることになる。
初めての黒人大統領ということで、過激な人種差別主義者によるオバマの暗殺など不埒なことが起きないことは祈りたいもの、だ。
そして、世界的に、日本を除いて、不動産バブル、株のバブルの崩壊が起きている。日本の株価下落は、その率が金融危機の本家である米国より落ち幅が酷いことから、明らかに、日本国内要因に依存すると考えられる。この点が、他国と日本の現象的な違いである。日本経済はデフレからの脱却途中であることが、大きな相違を生み出した原因である。
東アジアの中国、韓国は、金融緩和に踏み出し、中国は不動産融資の総量規制を緩和した。すなわちこれは、東アジアの政策転換であり、景気の回復へ中国当局が踏み出した政策転換である。
アジア新興諸国は、97年の通貨危機の後、所得に対する貯蓄の割合がそれほど変化なく、投資の割合が低いから、貯蓄より投資が多い経常黒字の経済状況である。それ故、米国への輸出依存が高いといえる。金融緩和が原因であるのだろうが、短期資本の流出により、新興国家の通貨が下落、それ故、アジア新興国の経済対策は、短期の投資の呼び込みより、設備投資などの長期に及ぶ投資の呼び込み政策、貯蓄を投資にまわすような税制などの内需喚起策に転換すべきだろう。参照図解 アジア経済
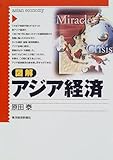
原油などの資源価格の世界総需要の減衰による下落、それのみならず小麦、とうもろこしなどの生活関連物資も半額程度にまで落ち込み下落推移の状況にある。世界景気の減速による総需要の減速は、実態的な生活空間では、7月ごろの生活物資の値上げラッシュで「物価」高と認識されているが、しかしながら最近の国際商品の先物の傾向は、金の価格を含めて全面安である。投機筋の資金が乱高下を誘導したとは言え、商品先物の現物の先行指標性は実需の予測の範囲にある。むしろ、世界総需要の減衰による価格低下というデフレの懸念を考慮に入れる段階に移っていると考えられる。
その意味では日銀の上記の国際商品の相場の下落による経済効果の指摘は正当でもある、といえる。但し、国内需要の喚起を日銀の量的金融緩和も目途に入れていないのは、政策当局による関与を放棄してしまっているようにしか筆者には映らないのだが・・・・・。デフレ懸念が当局にないのかもしれない・・・・。
与謝野氏の発言だが、日銀の金利の引き下げについて、「金融危機」に対応するものではないでしょ。株価下落で含み損を抱える金融資本の自己資金の毀損を修復するということを主とした対策ではない。日本の金融安定化法案の趣旨は、地方銀行、信金などの不良証券購入による貸与率の毀損を向上させる目的でなされる政策だと思う。そこが米国の金融危機とは趣を異にしている。
そこで、この法案を今国会で通さなければならないのが、政府、与党のもっとも重要かつ緊急の政治的イッシューであろう。
金利の引き下げは、株価と円、債券に影響を与えるが、金利の引き下げは、実体経済の下降懸念からの対策であると思うが・・・・。デフレ懸念に対する、景気に対する対応策だよね。
筆者は大日本帝国は、大まかな時代性の区分としてある時期に「侵略国家」として転化したと考える。はじめから侵略性を持っていたわけではなく、また国際環境も列強を中心として殖民国家であった国家が、戦闘行為に依存する国家から非戦的な国家へ転化した時期があると考える。第一次世界大戦後、ベルサイユ条約、4カ国条約---日英同盟廃止(これは後に失敗であった気づく)、九カ国条約など、日本の海軍には屈辱的ではあったが、均衡軍縮への国際道程が存在した。この方向に軍事官僚は、加藤寛治など海軍は反発。この国際情勢の変化の認識を欠如させたことも大いに手伝って、「侵略国家」化したのである。そのように考えないと、東條英機の東京裁判での弁明である軍部官僚たちの「自衛戦争」であったという言説が生まれてくる根拠もうまく説明が付かない。
筆者は、日本が「侵略国家」になったと認識できる時期のメルクマールは、国家を機関として見るか、機関のみならず国民としても眺める視点、戦争は相手が必要であるから、当然にその当時の国際関係の内実を見る視点、第一次世界大戦が産業から兵器の戦車、戦闘機、などの高度化、大量化、技術を持つ兵士訓練、兵站補給など総力を導入しなければ戦争の目的の達成が不可能になったという視点などから眺めるべきであると思う。また、統帥権の干犯問題が、浜口雄幸内閣を攻撃する犬養毅、鳩山一郎の政友会によって切って落とされた。統帥権は、軍人を管轄するのは天皇の大権であるとする。軍縮を浜口雄幸内閣は唱えたが、それが統帥権を干犯するとの説を、犬養毅、鳩山一郎、政友会は反論したのである。こうした議論を経て、軍部は統帥権干犯、天皇大権を犯すべからず論を立て、軍人の分限を弁えず、独走していくことになる。
一方、逆の作用も統帥権は持っていた。統帥権は明治期の「軍人勅諭」に由来するが、ここでは軍人は、「世論に惑はす政治に拘らす只(ただ)々一途(いちず)に己か本分の忠節を守り…」という訓戒がある。軍人は、政治に容喙してはならないということであり、明治中期まで文民統制の機能も持っていたのである。「田母神論稿」は、武官としての「本分」からも大きく外れていることになる。
国家の機関の現場の人士とそれを統制する「政治」側が、それぞれの役割を守っていることが必要。軍人の文民の統制は、有権者が選択した「政治」の側の権限であり、文民統制をするのは飽くまで「政治家」側の管轄になる。政治家側が、軍事権力を支配するという「思想」が有権者側と当時の新聞というマスコミ、ラジオ放送に強固にあれば、軍部の「暴走」は防ぐことは満州事変以前であれば出来たと思える。
更に、その戦闘は短期決戦ではなく、何年間にも及ぶ長期の「消耗戦」へと変化した。それまでの「戦争」の局所的、職業的な軍人による「短期」の戦い方からマスコミから一般の国民の戦争協力支援までを総動員した「総力戦」への戦い方に変更された、その視点などから見るべきであると思う。
そのように考えると「通常」の国家から「侵略国家」へ転化したのは、満州事変以降であろうと思う。満州事変は、周知のとおり石原莞爾によって「軍人勅諭」に反する形で遂行されたが、石原莞爾---一般の国民には、石原莞爾の名は知られていなかった----は第一次世界大戦以前にドイツに留学、総力戦が如何になされるかを知ったとされる。そして、総力戦を長期の戦争を戦費を欠けず、また、資源を満州に求め、産業を興し、戦争をすることによって資源開拓を行うことによって資源無き日本でも可能だとした。
満州事変の後、国連の査察結果に大きく反発する形で、この時点からマスコミは、満州以前の非戦的な風潮から好戦的な論調が澎湃、転生、またそれに賛意同調する「政治家」「庶民」も増えたと思える。その意味で、侵略国家はこの時期に誕生したのである。戦前を大づかみに見すぎて、侵略国家であった、また、無かったという議論は、極端すぎて実りある論争にはならないのではないか。それが繰り返されるとすれば非常に残念な事態である。
参照
東京裁判 (講談社現代新書 1924)
【ワシントン=五十嵐文】米大統領選は4日夜(日本時間5日朝)、全米各地で順次、開票が行われ、民主党のバラク・オバマ上院議員(47)が共和党のジョン・マケイン上院議員(72)を破り大勝した。オバマがすんなり当選。ブラッドリー効果も杞憂だったようだ。オバマのイラク戦争からの暫時の撤退には大きな同意をしたい。所詮、ゼロサムゲームである戦争などにほとんど利点は見受けることなど出来ない。ある特定の既得権益をもつ集団以外には利はない。元来イラク戦争は、ブッシュとブレアの「大儀」もなき間違った政策であった。大量破壊兵器も無い国へ、ブッシュドクトリン、先制攻撃は可能であるとするデマゴーギーによる「大儀なき」戦争であった。相互の退廃と憎悪を作り上げるゲームに過ぎない。しかしながら、アフガニスタンのテロの勢力との「対峙」は今後も継続されるのだろう。イラク戦争に反対したフランス、カナダなどはアフガニスタンのテロ勢力と対峙するという姿勢は強い。
オバマ氏は来年1月20日、第44代大統領に就任、米史上初の黒人大統領が誕生する。大統領就任時43歳だったジョン・F・ケネディ、46歳だったビル・クリントン両氏に続き、戦後では3番目に若い大統領となる。副大統領にはジョゼフ・バイデン上院議員(65)が就任する。
6年目に突入したイラク戦争や金融危機で米社会に閉塞(へいそく)感が充満する中、「変革」を訴えたオバマ氏に期待が集中し、人種の壁を打ち破った。民主党の政権奪回は、クリントン政権(1993~2001年)以来、8年ぶりとなる。民主党は、大統領選と同時に行われた上下両院選のうち上院でも過半数を維持した。
オバマ氏は、04年の前回選挙で共和党が勝利したフロリダ、オハイオ、ニューメキシコなどの各州を制したほか、44年ぶりにバージニア州も奪還。NBCテレビによると4日午後11時(日本時間5日午後1時)過ぎの時点で、選挙人数は当選に必要な270人を大きく上回る333人に達した。
オバマ氏は選挙戦で、米史上最低レベルの支持率にあえぐブッシュ政権との違いを強調した。外交ではイラク駐留米軍の早期撤退を公約。9月に金融危機が深刻化し、経済の立て直しが最大の争点となると、金融市場に対する規制強化など暮らしに配慮した政策を打ち出し、支持を拡大した。
ケニア出身の黒人の父、米国人の白人の母の間に生まれたオバマ氏は、人種や党派の違いを超えた「統合」を訴え、若者を中心に「オバマブーム」を巻き起こした。
(2008年11月5日14時03分 読売新聞)
米国からの民主勢力に強かったかつての自動車輸出バッシングなど起きることはないだろう。トヨタ、ホンダはすでに現地生産、現地販売に多くをシフトし、現地の雇用を生み出しているからである。
オバマの米国経済の建て直しと長期的戦略による米国の経済構造を変更させることが出来るのかが、日本の経済にとっては重大な事態でであるはず、である。一挙に「消費から貯蓄」への社会構造になるとすると、これはこれで、米国輸出依存の日本経済にとっては直近の大きな痛手である。 米国の消費で、輸出が支えられているアジア諸国家の成長性補償されている現状に目を向けるとその点が大きな短期的、経済循環的には関心事なることになる。
初めての黒人大統領ということで、過激な人種差別主義者によるオバマの暗殺など不埒なことが起きないことは祈りたいもの、だ。
豪が0・75%利下げ=5・25%に
【シドニー4日AFP=時事】オーストラリア準備銀行(RBA、中央銀行)は4日、政策金利を予想を上回る0・75%引き下げ、5・25%とした。
RBAは、現在の世界および国内の情勢を考慮すれば政策金利のかなり大幅な引き下げも許容されるとしている。
スティーブンズRBA総裁は声明で、今後も情勢のチェックを継続し、2-3%のインフレ目標の達成と一致する持続可能な成長を促進するのに必要な調整を行っていくと述べた。〔AFP=時事〕
前向きの循環メカニズム、2010年度に再び明確に=日銀展望リポートメモ的に示すと日本経済の米国に対して輸出シェアが3割程度、中国、マレーシア、インドネシア、などの東南アジア新興国に対する日本の輸出シェアはほぼ5割である。輸出依存である日本だが、その輸出割合が、90年代より2000年代は東南アジアにも依存している。
【東京 4日 ロイター】 日銀は4日に公表した「経済・物価情勢の展望」(展望リポート)の全文で、日本経済の先行きについて、2010年度には輸出・生産を起点とした前向きの循環メカニズムが再び明確になる、との見通しを示した。
日銀は日本経済について、2009年度半ば頃までは停滞色の強い状態が続く可能性が高いと指摘。2009年度半ば頃からは、1)国際金融資本市場や米欧の金融システムが安定化に向かい、海外経済が減速局面を脱していくこと、2)国際商品市況が総じて安定的に推移すること──を前提に、輸出と国内民間需要がともに回復基調を取り戻し、日本経済の成長率は潜在成長率へ次第に近づいていく、との見通しを示した。
その上で、2010年度に関しては、1)海外経済が高めの成長を取り戻す、2)国際商品市況が上昇するとしてもそのテンポは緩やかなものにとどまる── ことを条件に、輸出・生産を起点とした前向きの循環メカニズムが再び明確となり、金融緩和効果も強まっていく、との見方を示した。
カギを握る海外経済については、2010年度までに「持続可能な成長経路に復していく」と予想したが、「再び5%まで達するとは想定しにくい」とも指摘。さらに「先行きのシナリオについては、大きな不確実性が存在している」と警戒感も示した。
企業収益が減少を続けるもとで弱めの動きとなっている設備投資に関しては、金融緩和効果が次第に強まると予想されることなどから「伸び率は次第に回復する」とみているが、同時に「2008年度から09年度の落ち込みが限定的であるとすれば、2010年度については、2003年度から06年度までのような高い伸びとなるがい然性も低い」との見方も示した。
2008/11/04 16:17
そして、世界的に、日本を除いて、不動産バブル、株のバブルの崩壊が起きている。日本の株価下落は、その率が金融危機の本家である米国より落ち幅が酷いことから、明らかに、日本国内要因に依存すると考えられる。この点が、他国と日本の現象的な違いである。日本経済はデフレからの脱却途中であることが、大きな相違を生み出した原因である。
東アジアの中国、韓国は、金融緩和に踏み出し、中国は不動産融資の総量規制を緩和した。すなわちこれは、東アジアの政策転換であり、景気の回復へ中国当局が踏み出した政策転換である。
アジア新興諸国は、97年の通貨危機の後、所得に対する貯蓄の割合がそれほど変化なく、投資の割合が低いから、貯蓄より投資が多い経常黒字の経済状況である。それ故、米国への輸出依存が高いといえる。金融緩和が原因であるのだろうが、短期資本の流出により、新興国家の通貨が下落、それ故、アジア新興国の経済対策は、短期の投資の呼び込みより、設備投資などの長期に及ぶ投資の呼び込み政策、貯蓄を投資にまわすような税制などの内需喚起策に転換すべきだろう。参照図解 アジア経済
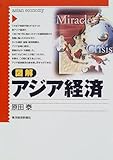
原油などの資源価格の世界総需要の減衰による下落、それのみならず小麦、とうもろこしなどの生活関連物資も半額程度にまで落ち込み下落推移の状況にある。世界景気の減速による総需要の減速は、実態的な生活空間では、7月ごろの生活物資の値上げラッシュで「物価」高と認識されているが、しかしながら最近の国際商品の先物の傾向は、金の価格を含めて全面安である。投機筋の資金が乱高下を誘導したとは言え、商品先物の現物の先行指標性は実需の予測の範囲にある。むしろ、世界総需要の減衰による価格低下というデフレの懸念を考慮に入れる段階に移っていると考えられる。
その意味では日銀の上記の国際商品の相場の下落による経済効果の指摘は正当でもある、といえる。但し、国内需要の喚起を日銀の量的金融緩和も目途に入れていないのは、政策当局による関与を放棄してしまっているようにしか筆者には映らないのだが・・・・・。デフレ懸念が当局にないのかもしれない・・・・。
【円・ドル・人民元 通貨で読む世界】半端な利下げ、こすいぞ日銀2008年11月3日(月)08:05 産経新聞
白川方明(まさあき)総裁にはあぜんとさせられた。10月31日の政策金利の0・2%引き下げ決定後の記者会見で、総裁は「経済情勢、金融情勢自体がこの1カ月弱の間に大きく変化した」と言いのけた。1カ月弱前とは前回の日銀政策決定会合が開かれた10月6、7日を指す。9月15日の米証券大手リーマン・ブラザーズの経営破綻(はたん)をきっかけに米国発の危機は全世界に飛び火し、ただちに日本にも及んでいた。なのに日銀は情勢を甘く見ていた。それを示すのが「幻の緊急声明」事件である。
10月7日午後6時半、麻生太郎首相は、11日にワシントンで開かれる先進7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)出席のため出発する中川昭一財務・金融担当相と並んで白川総裁を首相官邸に呼んだ。首相の意図は、「日本のバブル崩壊時の教訓を米側に伝えよ」という指示だとされるが、首相の手元にはある素案があった。
「金融危機に対する日本の決意のほどを緊急声明にして発表しようというもので、日銀によるふんだんな資金供給がその柱の一つだった」(政府筋)。ところが、日銀は同案に返事をせず、事実上無視。結局声明案は流れた。雑誌ファクタ11月号では「(危機への対応は)やくざな性分でなきゃできないな」との麻生首相の発言を紹介しているが、このときも出たに違いない。
8日にはさらに、米欧など世界10カ国の中央銀行が協調利下げにも踏み切ったが、日銀は米連邦準備制度理事会(FRB)などからの要請を断っていた。結果は、その後の急激な円高、株安。そしてすでに下降局面に入っている景気の先行き不安へのだめ押し。10月末の銀行間の短期資金融通市場(コール市場)の残高は、6月末比で25%も減った。金融機関は企業向けに貸せない。
今回の0・2%利下げは何を意図するのか。もとより、金利水準は「超低金利」である。わずかに下がっても、実体経済への刺激効果に乏しい。信用収縮とデフレ懸念でいつ一部金融機関が破綻してもおかしくない今、日銀に求められるのは、緊急措置としての「量的緩和」のはずである。ところが、日銀の意図はあいまいだ。
日銀は日銀券を刷り市場に流し込む。この上限を大幅に引き上げるのが量的緩和なのだが、そうするとコール市場では資金が余り、短期金利は下落を続け、究極的には金利ゼロになる。日銀はそうなると短期金融市場を操作できなくなるので嫌う。
従来の0・25%の利下げ幅を拒否したのは、もう一度利下げすればゼロになるからだ。ご丁寧なことに、銀行の日銀への当座預金に金利を付け、短期市場金利がそれ以下にならないようにした。日銀は量的緩和に歯止めをかけゼロ金利を避ける、というのが今回の利下げの真相なのである。とすれば、日銀は自身の利害を優先して危機対策という大局を見ない、狡(こす)いやり方ではないか。(編集委員 田村秀男)
日銀の利下げを歓迎、金融危機に立ち向かう姿勢示した=与謝野担当相
【東京 31日 ロイター】 与謝野馨経済財政担当相は31日、日本銀行の利下げを受けて会見し、日銀の決定を歓迎すると述べた。利下げの効果については「目を見張るほどの効果を期待してはいけない」としながらも「日銀も金融危機に立ち向かう姿勢を示し、国際金融社会とともに歩む姿勢を示したもので、高く評価する」と述べた。
また、「国内の経済対策や国際協調との整合性においても、政府として、日本銀行の決定を評価したい」と指摘。国際金融市場や11月15日に米国で開催される金融サミットに対して「当然、国際的な金融危機に対して隊列を整えて取り組んでいるという極めて重要な、象徴的な意味がある」と述べた。
一段の利下げ期待に関しては「(政策変更前の政策金利水準は0.5%で)もともと背丈があまり高くない。それでも、率からいうと4割下げたともいえる」と語った。
与謝野担当相は欠員となっていた日銀副総裁人事補充で積極的な役割を果たしたことが知られているが、今回の利下げ決定では賛否同数で議長が決した形となり、欠員となっている審議委員について「早急に国会の同意を得て、1人補充しなければならないとあらためて感じた」と語った。
(ロイター日本語ニュース 吉川 裕子記者)
与謝野氏の発言だが、日銀の金利の引き下げについて、「金融危機」に対応するものではないでしょ。株価下落で含み損を抱える金融資本の自己資金の毀損を修復するということを主とした対策ではない。日本の金融安定化法案の趣旨は、地方銀行、信金などの不良証券購入による貸与率の毀損を向上させる目的でなされる政策だと思う。そこが米国の金融危機とは趣を異にしている。
そこで、この法案を今国会で通さなければならないのが、政府、与党のもっとも重要かつ緊急の政治的イッシューであろう。
金利の引き下げは、株価と円、債券に影響を与えるが、金利の引き下げは、実体経済の下降懸念からの対策であると思うが・・・・。デフレ懸念に対する、景気に対する対応策だよね。
カレンダー
リンク
カテゴリー
最新コメント
[10/17 coach outlet]
[10/15 ティンバーランド ブーツ]
[10/11 モンクレール ever]
[10/11 コーチ バッグ]
最新記事
(06/22)
(06/11)
(01/22)
(12/01)
(09/06)
(08/16)
(08/11)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
解 龍馬
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(09/20)
(09/21)
(09/25)
(09/26)
(09/27)
(09/28)
(09/29)
カウンター
アクセス解析
フリーエリア
組織の中の人

